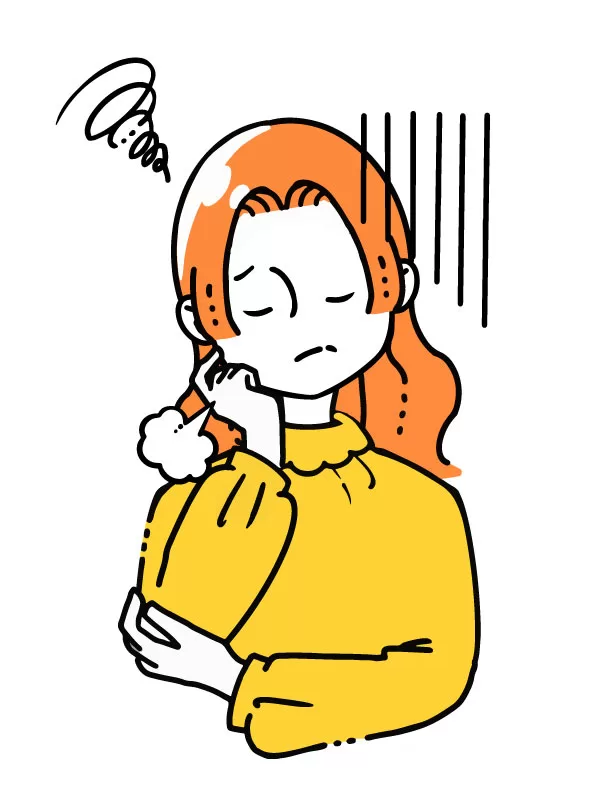
象印のスチーム式加湿器、人気ですよね。私もすごく気になっています。
でも、電気代が心配なんです。
その気持ち、わかります。しかし、心配はいりません。
最近の加湿器は省エネ設計がなされており、必要以上に電力を消費することはありません。
筆者は、断言します。
電気代は、使用時間や使うタイプ(大きさ)により異なる異なるため一概には言えませんが、『ひかえめ・弱』での運転をすれば問題になるほど高いものではありません。
音波式だと、家具が汚れるし雑菌の心配があるので、多少電気代があがってもスチーム式が最強です。
だからこそ、象印スチーム加湿器は人気なんです。
8年前からの象印加湿器の愛用者。
一家に3台保有しています。
今年の電気代が値上がりしているのでSANWAワットモニターで家電電力を調査。
象印加湿器の中でも、もっとも電気代が安い小型(20サイズ)の新型加湿器EE-Ⅿ型を強くおすすめします。
正直言って購入を検討中です。

象印加湿器の電気代
今回は、東京電力の料金プランを参考に、3人以上の家庭で平均的な第三段階料金1kWhあたり40.49円で計算します。
「しっかり」運転で1時間使うと、約16~11円かかります。
「標準」運転では、約15~10円です。
「ひかえめ」運転の場合は、さらに安く13~8円以下です。
※EE-M型の『標準』運転なら7~5.5円です。
※EE-M型の『静穏』運転なら5~3円です。
電気代に幅があるのは、象印加湿器のサイズにより基本消費電力がことなるからです。
電気料金は、住む場所や契約アンペア、電力会社によって異なります。
ご自身の電気料金プランを確認し、1kWhあたりの単価を調べてから、この記事の数値を参考に計算してください。
また、使用時間や運転モードによっても電気代は変動します。
スチーム加湿器の消費電力は、お湯を沸かす時に一番消費します。
節電をしたいなら、ぬるま湯やお湯を使って加湿すると良いでしょう。
(お湯を沸かすために電気消費が激しくなるため)
引用の数字からもわかるように、大きいサイズほど電気代が高くなります。
小さいほど基本的な消費電力が少なくなり、電気代も安くなります。
機種やサイズによりかなりの差が出ることが表示されています。
以下の数字は、2025年の象印マホービン公式ページより引用してますが、電気代は、新電力料金目安単価31円/kWh(税込)を基に算出しているので現実の支払いより少し安く出ています。
●EE-D型
強運転(加湿時)で1時間当たり
35サイズ:約9.1円
50サイズ:約11.9円
加湿開始までの湯沸し時(水温20℃・満水状態)
35サイズ:約15.3円
50サイズ:約17.8円●EE-M型
標準運転(加湿時)で1時間当たり
20サイズ:約5.5円
加湿開始までの湯沸し時(水温20℃・満水状態)
20サイズ:約10.1円●EE-R型
強運転(加湿時)で1時間当たり
35サイズ:約8.8円
50サイズ:約11.9円
加湿開始までの湯沸し時(水温20℃・満水状態)
35サイズ:約10.2円
50サイズ:約12.7円●EE-T型
強運転(加湿時)で1時間当たり
60サイズ:約14.3円
加湿開始までの湯沸し時(水温20℃・満水状態)
60サイズ:約17.8円(当社基準による測定)
※電気代は、新電力料金目安単価31円/kWh(税込)を基に算出
この電気代は、全国平均目安を採用していますが、一般家庭(3人以上)では、第三段階料金(40円/kWh)になることがほとんどです。
我が家は、3台所有してますが古いベーシックタイプです💦
3Lのタイプ(加湿時305W)と4Lのタイプ(加湿時410W)の2種があり3Lが基本消費電力が少ないです。
基本的にサイズが大きいものほど、消費電力が大きくなります。
そして、新型の加湿器のほうが節電に適した湿度調整機能がついていてお得です。
昨年新発売のされたEE-M型は、超小型サイズでシンプル機能で電力消費量が少なくお勧めです。
EE-M型
標準運転(加湿時)で1時間当たり
20サイズ:約5.5円
加湿開始までの湯沸し時(水温20℃・満水状態)
20サイズ約10.1円
データは、公式ページより引用してます。
Amazonで検索して確認象印加湿器の「結露問題」解決法
象印加湿器の「結露問題」は、部屋の湿度をあげすぎるからおきます。
部屋の湿度を35~40%程度に調整しながら使うことでかなり結露を抑えることができます。
2024年モデルの象印加湿器は、「湿度センサー」「室温センサー」のデュアルセンサーが快適な湿度を自動コントロールするデュアルセンサーがついてます。
部屋の湿度がわかる「湿度モニター」で湿度を低湿にしておけば、ひどい結露はおきにくいです。
一般的に室温が20℃程度の場合、相対湿度40%以下であれば、窓や壁での結露が発生しにくいと考えられています。
つまり、湿度計を使って35~40%に湿度を調整すれば結露問題は解決します。
ただし、外気温や窓の断熱性能などによって、結露が発生する湿度は変動します。
【結露しやすくなるパターン】
①外気温が低い場合:
外気温が低いほど、窓や壁が冷えやすくなり、結露が発生しやすくなります。
②窓の断熱性能が低い場合:
単板ガラスなど断熱性の低い窓は、表面温度が下がりやすく、結露が発生しやすくなります。
結露は、温度差の問題もあるので加湿器のせいだけではないことも覚えておいてくださいね。
暖房器具の電気代は、使用時間や設定温度、部屋の断熱性などによって大きく変わるので、ご自身の使用状況に合わせて参考にしてください。
スチーム加湿器のデメリットである結露問題などを考えると『控えめ』の弱で使うことをおすすめします。
加湿器の効率の良い置き場所
まず、一番大切なことは、加湿器はできるだけ部屋の真ん中に置くこと。もしくは、家の中心側の壁側に置きましょう
そして、床に直置きするよりも、少し高い場所に置くのがおすすめです。
なぜかというと、
* 部屋全体を加湿するため:
部屋の真ん中に置くことで、加湿された空気が部屋全体に行き渡りやすくなります。
* 効率よく加湿するため:
高い場所に置くことで、加湿された空気が上から下に広がりやすくなり、効率よく部屋を加湿できます。
電気代と結露対策!置き場所でこんなに変わる!
加湿器の置き場所を工夫することで、電気代の節約にもつながるって知ってましたか?
部屋全体を効率よく加湿できれば、加湿器のパワーを上げすぎる必要もなくなるので、電気代の節約にもなるんです。
さらに、結露を防ぐためにも、置き場所はとっても大切です。特に、
* 出窓やガラス窓の近くは避ける:
窓の近くは温度が低くなりやすく、結露が発生しやすい場所です。加湿器を置くと、さらに結露がひどくなってしまう可能性があります。
* 水に弱い電化製品の近くも避ける:
加湿器から出る水蒸気は、精密機器にとっては大敵です。故障の原因になることもあるので、できるだけ離して置きましょう。
プラスワン!珪藻土マットで水滴対策
加湿器のフタを開けた時に、水滴がポタポタ落ちてくること、ありますよね?
そんなときは、加湿器の下に珪藻土マットを敷いておくのがおすすめです。
珪藻土マットは吸水性が高いので、水滴をしっかり吸い取ってくれます。
まとめ:加湿器の置き場所で電気代節約と結露問題解決!
* 部屋の真ん中、少し高い場所もしくは、家の中心側の壁側
* 窓際や電化製品の近くは避ける
* 珪藻土マットで水滴対策

おすすめの使用方法
スチーム式加湿器のメリットを活かす方法
スチーム式加湿器の魅力は、なんといってもその加湿力と保温力です。
音波式加湿器とは違い、雑菌の心配がないのは大きなメリットでしょう。
家具が汚れる心配もなく、お手入れも簡単なので、毎日気持ちよく使えます。
しかし、それだけではありません。
湿度と温度をほどよく保つためには、エアコンやサーキュレーターと組み合わせて使うのがおすすめです。
そうすることで、より快適な空間を作ることができますよ。
スチーム式加湿器のデメリットを減らす方法
スチーム式加湿器のデメリットは、電気代がかかることと、結露が発生しやすいことです。
電気代を少しでも減らすため、また結露を防ぐためにも、部屋の湿度計を確認しながら運転モードを切り替えることが大切です。
部屋の湿度を40%前後に保つようにしましょう。
結露がひどくなる前に、「ひかえめ」モードに切り替えるか、運転を止めるようにしましょう。
エアコンの乾燥を防ぐ目的で併用すると、加湿のバランスが良くなります。
エアコンの設定温度を下げられるというメリットもあるので、スチーム式加湿器とエアコンの組み合わせは、まさにゴールデンコンビと言えるでしょう。
春のスギ花粉対策には、空気清浄機と組み合わせて使うのも効果的です。
まとめ
✅「しっかり」運転 約16円
✅「標準」運転 約14.7円
✅「ひかえめ」運転 約13.3円以下
※2025年東京エリアの第三段階での目安です
✅EE-M型の『標準』運転なら7~5.5円です。
✅EE-M型の『静穏』運転なら5~3円です。
電気代を節約したい方は、使用時間や「ひかえめ」運転をおすすめします。
電気代だけで考えるなら、小型サイズのEE-M型がもっもおすすめです。
- 湿度に合わせて運転のレベルを調整する。
- 部屋の中央に置く(できれば高い場所)
- エアコンやサーキュレーターと組み合わせて使う
結露は置き場所を工夫したり、湿度を調整したりすることで、ある程度対策できます。
電気代は運転モードを『ひかえめ』弱運転にして小型サイズを選択することでかなりの節電ができます。
スチーム式加湿器は、一家に一台あると本当に便利です。
ぜひ、検討してみてください
合わせて読みたい記事『象印・加湿器のデメリットとメリット【7年以上愛用者が語る】』
この記事についての意見や悩み、疑問、質問などがありましたら、ご自由にコメント欄に投稿して下さい。
※いただいたコメントは全て拝見し真剣に回答させていただきます。
応援よろしくお願いします。
人気ブログランキング
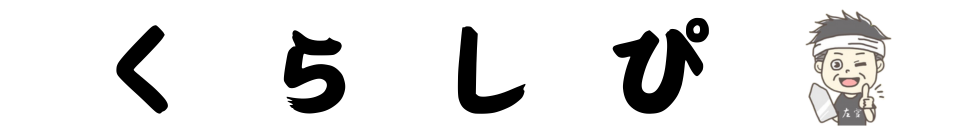











コメント